当ブログはアフィリエイト広告を利用しています。
この本が気になっているあなたへ。
私には4人の子どもがいます。
そのうち2人が、発達ユニークな子どもたちです。
最初に診断を受けたとき、「発達障害」という言葉に正直ショックを受けました。
でもこの本に出会って、「ユニークな子」と表現してもらえたことに、心がふっと軽くなったんです。
うちの小2の娘は、「私の特技は学校いけないこと!」って、笑いながら話します。
宿題も「そんなん別にしなくていいやん?」って(笑)
「私ね、特技あるよ!学校行けないこと!」
と胸を張る小2娘🧒母は驚きすぎてフリーズしたけど、その瞬間なんだか救われた🥹
深刻に悩んでたのに、本人は笑い飛ばしてしまう😂
生きづらさをユーモアに変える力って、本当に才能だと思う👍
子どもの発想って時に親を支えてくれる✨
— 藤本サクラ@不登校と向き合う母 (@u2jS3kswIG55477) August 23, 2025
そんなユニークな子どもの発想に、いつしか救われているのは私のほうかもしれません。
この記事では、そんな私自身の経験もふまえて、この本のやさしさと力強さをレビューしています。
読んだあと、きっとあなたも「うちの子って、すごくユニークかも」って思えますよ。
発達ユニークな子 レビューでわかる7つの気づき
ここでは「発達ユニークな子が思っていること」を読んで得られる7つの気づきをご紹介します。
①子どもが本当に困っている理由
この本では、発達ユニークな子どもたちが、なぜ困ってしまうのかがとても丁寧に書かれています。
一見すると「わがまま?」「反抗的?」と誤解されがちな行動も、
実は“感覚のズレ”や“認知の違い”からきていることがあるんですね。
本人たちも「困らせたい」わけではなく、「困っている」のだという視点がとても大切に描かれていて、親としてもハッとさせられました。
たとえば、
- 音が大きすぎて集中できない、
- 服のタグがチクチクして気が散る
など、感覚過敏に関するエピソードがいくつも紹介されています。
こうした理解があるだけで、
「なんでできないの?」から
「どうすればできるかな?」に気持ちが変わるんです。
読んでいると、「うちの子も、こういうこと言ってたな…」と自然に思い出されて、共感とともに涙が出てくる場面もありました。
子どもが感じている世界を、少しでも“同じ目線で見てみよう”と思えるようになりました。
②発達ユニークな見方が優しい

この本では、「発達障害」ではなく「発達ユニーク」という言葉が使われています。
その言葉選び自体が、とってもやさしくて希望にあふれているんですよね。
「ユニーク」って聞くと、なんだか面白くて個性的で、悪い意味じゃなくて“光る何か”があるような感じがしませんか?
そう、この本は“できないこと”にフォーカスするのではなく、
“その子なりの感じ方・考え方”に目を向けてくれています。
読んでいて「こういう言い方をするだけで、ずいぶん救われる人がいるんじゃないかな」と思いました。
子どもの世界にそっと寄り添いながら、でもしっかりと支える、そんなあたたかさがにじみ出ていますね。
医師である著者が、専門用語をなるべく使わずに書いているのもポイントです。
③「問題児」じゃなく「特性」と見る
大人の目線から見ると、「この子は問題がある」と感じてしまうことって、正直ありますよね。
でもこの本では、そんなふうに決めつけてしまう前に、
「その行動にはどんな背景があるんだろう?」
という視点を持つことの大切さが描かれています。
たとえば、
「授業中に席を立つ」
「順番を守れない」
「すぐキレる」
といった行動も、実は“その子なりのSOS”だったりします。
子どもたちの行動の裏にある「理由」を知ることで、大人の対応が変わるんですね。
これは、子育てや教育の現場にいるすべての人に響く内容だと感じました。
そしてなにより、「その子は悪くない」というメッセージが、じんわりと心に沁みます。
一人ひとりの“特性”に気づき、それを“理解しよう”という視点を持つだけで、まったく違う関わり方ができるようになります。
④親や先生の気持ちにも寄り添う
この本のすごいところは、「子どもを支える側の気持ち」にも深く寄り添ってくれる点です。
「こんなに頑張ってるのに、なんで伝わらないんだろう…」
「私はちゃんとできてるのかな?」
そんなふうに不安や孤独を感じている親御さんや先生に向けて、優しい言葉がたくさん散りばめられています。
「完璧じゃなくていいんですよ」
「できているところを見てくださいね」
そう言われるだけで、心の重荷がすっと軽くなるような感覚がありました。
子どもを変えるんじゃなくて、大人が“自分を責めない”ことから始めてもいいんだなって、勇気をもらえます。
⑤子ども目線で書かれている
この本は、すべて“子ども側の気持ち”を第一にして書かれているのが特徴です。
「どうして怒られるのか、分からなかった」
「言いたいことがあるけど、うまく伝えられない」
こうした子どもの“声にならない声”が、文章としてとてもていねいに表現されているんです。
大人が気づきにくい部分、見落としてしまいがちな感情に、そっとスポットライトが当てられています。
読みながら、何度も「ああ、こう感じてたのかもなあ…」と胸が熱くなりました。
子ども目線のリアルな描写が、読者の心に響く力を持っています。
⑥接し方のヒントがたくさんある
「じゃあ、どうすればいいの?」
読者が一番知りたい部分にも、ちゃんと答えてくれているのがこの本の魅力です。
たとえば、
「まずは話を最後まで聞いてあげる」
「やってほしいことを一つに絞って伝える」
など、すぐ実践できるアイデアがたくさん載っています。
専門書というよりは、“日常のちょっとしたコツ集”のような感覚で読めるので、忙しい親御さんにもぴったり。
肩の力を抜きつつ、「あ、これやってみようかな」と思える内容ばかりでしたよ。
⑦読んだあとに心が軽くなる
この本のいちばんの魅力は、“読後感”かもしれません。
重いテーマのように見えて、読んでみると心がふんわり軽くなるんです。
「子育てって、がんばりすぎなくていいんだ」
「この子を信じてあげよう」
そんな風に、ちょっと前向きになれる言葉がたくさん詰まっています。
きっと、読み終わったあなたも「この子と、もっと仲良くなれそう」って思えるはずです。
精神科医さわってどんな人?
著者である精神科医さわ先生について知ると、本の信頼感がぐっと増しますよ。
①子ども専門の精神科医としての実績
さわ先生は、子どもの発達やこころの問題に向き合ってきた精神科医です。
特に「発達障害」「不登校」「親子関係」などに関する診療を長年行っており、現場で培われた知見がこの本にも反映されています。
病院や支援機関での実際の相談経験があるからこそ、読者の悩みに“的確な言葉”で寄り添えるのだと感じました。
専門用語よりも、やさしい表現を使ってくれているのが嬉しいですね。
難しい話をわかりやすく届けてくれる、信頼できる専門家という印象です。
②SNSでも人気の信頼できる先生
実は、さわ先生はTwitter(X)などSNSでも多くの支持を集めているんです。
こんにちは。精神科医さわです。
私は、ふだん名古屋市にて、5歳以上から大人までを対象としたメンタルクリニックの院長をしています。
「落ち着きがない子」
「忘れっぽい子」
「こだわりが強い子」
「勉強が苦手な子」など、周りになかなか馴染めない… pic.twitter.com/Mo35UP8aBr
— 精神科医さわ@5万部『子どもが本当に思っていること』著者 (@CocoroDr_Sawa) August 14, 2025
発達に関する悩みや親子関係のヒントを、とても温かく発信されていて、読者との距離感がとても近いんですよね。
この本を読んで「この先生の考え方、好きかも」と思った方は、ぜひSNSもチェックしてみてください。
一貫しているのは、「子どもの味方であり、大人の味方でもある」という姿勢です。
その優しさが文章にも表情にもあふれています。
③深い経験からくる言葉の力
読んでいて心に残ったのは、さわ先生の“言葉の力”でした。
押しつけるようなアドバイスではなく、「こういうふうに考えてみませんか?」とそっと手を差し伸べてくれる感じ。
それは、やはり長年現場に立って、たくさんの親子を見守ってきた経験からくるものだと思います。
「きっと先生も、たくさん悩んできたんだろうな」と感じられるからこそ、言葉に重みがあるんですね。
ただの知識じゃない、“生きた知恵”をもらえるような感覚がありました。
さらに胸を打たれたのは、さわ先生ご自身も、発達障害の診断を受けた2人の娘さんの母であるということ。
精神科医という専門職でありながら、「もう限界かも…」と思った日があったことを、正直に綴ってくれています。
母としての不安、悩み、自分を責めた経験──。
それを包み隠さず書いてくださったからこそ、「この人の言葉は信じられる」と思えたのだと思います。
親としての孤独や戸惑いを、誰よりも分かってくれている先生です。
心に残る名言とストーリー

ここでは、読者の心に刺さる名言や、印象的なエピソードをご紹介します。
①感覚の違いがよくわかる話
「普通の子は気にしないことでも、発達ユニークな子には“世界が違って見えている”」
この一文がとても印象に残りました。
たとえば、教室の蛍光灯のチカチカや、鉛筆の音、給食のにおい…
そんな“気づかれにくい違和感”を、本人はずっと我慢していることがあるんです。
「だから集中できないのか」
「落ち着かないのも仕方ないよね」
って、やっと気づけました。
“感覚の世界”に目を向けることで、見えなかった背景がクリアになる感覚がありました。
②「学校がつらい」理由に納得
学校に行きたがらない子って、最近増えていますよね。
でも、それが「甘え」ではなく、「本当にしんどい」こともあるんだって、この本は教えてくれます。
・集団行動が苦手
・同じ空間に長時間いるのがつらい
・自分だけが理解できていないと感じる
そんな“居場所のなさ”が、学校でのつらさの正体だったんですね。
先生や親が「学校は行くもの」と決めつける前に、なぜつらいのかを一緒に考えてみる。
その大切さに気づかされました。
③「親に言えない気持ち」が胸に刺さる
「お母さんを困らせたくない」
そんな思いから、自分の本当の気持ちを言えずにいる子もいます。
本の中には、そうした“子どもなりの気遣い”がいくつも描かれていて、読んでいて涙が出そうになりました。
大人から見れば「言ってくれればいいのに」ですが、子どもには子どもなりの“親への思いやり”があるんですね。
親も子も、どちらも頑張ってる。
そんな事実に気づけるだけで、関係が少しやわらかくなる気がしました。
④特に印象的だった場面は?
印象に残ったのは、「その子が笑った瞬間」について書かれていたエピソードです。
ずっと緊張していた子が、ある日ぽろっと笑った。
それだけで周囲の大人たちは、「この子にもこんな表情があったんだ」と驚いたそうです。
「笑う」って、すごくシンプルだけど、“安心してる証拠”なんですよね。
その子にとって安心できる環境が、少しずつ広がっていく様子が伝わってきて、心があたたかくなりました。
こんな人におすすめしたい本
この本を読んでほしいのは、発達に悩む子どもたちだけではありません。
むしろ、子どもに関わるすべての大人にこそ読んでほしい1冊です。
①「うちの子だけじゃない」と思える
日々の子育てで、「なんでこの子だけ、こんなに大変なんだろう…」と感じたことはありませんか?
この本を読むと、「同じような悩みを抱えている子や親はたくさんいるんだ」と思えます。
「発達ユニーク」という言葉に置きかえるだけで、子どもの姿がちょっと違って見えてくるんです。
「できないこと」ではなく「その子らしさ」に目を向けられるようになりますよ。
自分だけじゃない、という安心感って、すごく大きいです。
②子どもとの接し方がやさしくなる
子どもにイライラしたり、つい強く言ってしまうことって、誰にでもありますよね。
でも、この本には「こうすればいいよ」という押しつけはなくて、
「こういう考え方もあるよ」とそっと差し出してくれます。
そのおかげで、ガチガチだった心がふっとやわらかくなって、「ちょっと試してみようかな」と思えるんです。
たとえば、「1つずつお願いする」「まずは共感から始める」など、明日から実践できるヒントがたっぷり詰まっています。
子どもとのコミュニケーションがスムーズになるだけで、毎日がちょっと楽しくなりますよ。
③親の心がふっと軽くなる
一番グッときたのは、「子どもを変える前に、自分を責めないでいい」というメッセージです。
親ってつい「私がちゃんとできてないから…」と自分を責めがちですが、この本はまず親の心をふわっと包んでくれるんです。
「毎日よく頑張ってますよね」
「まず自分をほめてくださいね」
って、先生が言ってくれるような感覚。
頑張っている親の背中を、そっと押してくれる本だなと思いました。
心がつらくなったとき、そっと手に取りたくなる1冊です。
発達ユニークな子 レビューのまとめ

ここでは、『発達ユニークな子が思っていること』を読んで感じた総まとめをお伝えします。
買うか迷っている方、どんな人に向いているか知りたい方へ向けて、わかりやすく整理してみました。
①読む前に知りたい人へ向けて
この本は、発達に関する専門書というよりも、エッセイに近い感覚で読めます。
専門知識がなくても読めるようにやさしい言葉で書かれていて、忙しい合間にも少しずつ読めるのがポイントです。
「子どもがちょっと気になるな」と思っている親御さんや、「もっと子どもに寄り添いたい」と考える先生にぴったりです。
悩んでいる人が、ほんの少し前向きになれる──そんなやさしい本だと心から思いました。
悩みが大きくなる前に、読んでみてほしい1冊です。
②似た本とのちがいも紹介
発達に関する本はたくさんありますが、特徴はなんといっても“やさしさ”と“リアルな声”です。
たとえば専門書では『発達障害の子どもを育てる親の本』や『子どもが育つ魔法の言葉』などが有名ですが、それらと比べても本書は「読むとホッとする」部分が強いです。
知識や理論ではなく、エピソードと共感で構成されているので、肩ひじ張らずに読めるんですね。
感情に寄り添う本、という意味では他にあまり見かけないタイプかもしれません。
理屈よりも「心」で受け取りたい人にとっては、とても相性のいい本です。
③紙のみ発売!手元に置いておきたくなる理由
2025年8月時点で、電子書籍版はまだ発売されていません。
ですが、この本は“紙で読む価値”があるなと感じました。
理由は、何度も読み返したくなる言葉がたくさんあるから。
ふとしたときに開いて、気になるページをめくる…そんな読書スタイルが似合うんです。
落ち込んだ日や、子育てに疲れたときにパラパラと読み返すと、また元気が湧いてきますよ。
本棚にそっと置いておきたい、そんな1冊になるはずです。
発達ユニークな子は、まさに“ユニーク”だった。

「発達障害」と聞くと、重たい響きに感じてしまうかもしれません。
でも『発達ユニークな子が思っていること』という本は、
その言葉のイメージを、やさしく、あたたかく、ひっくり返してくれました。
子どもは、問題じゃない。
ただ、ちょっと世界の見え方が違うだけ。
「私の特技は学校いけないこと!」と笑う娘の姿に、私はどれだけ救われたことでしょう。
大切なのは、“どう直すか”ではなく、“どう関わるか”。
本書には、そんな大切な気づきが、たっぷり詰まっています。
同じように悩んできた親だからこそ、感じたこと。
あなたが今、少しでも不安やモヤモヤを抱えているなら──
この本を、ぜひ手に取ってみてください。
きっと、心が少しだけ軽くなって、
「この子と、もっと仲良くなれる気がする」と思えるはずです。
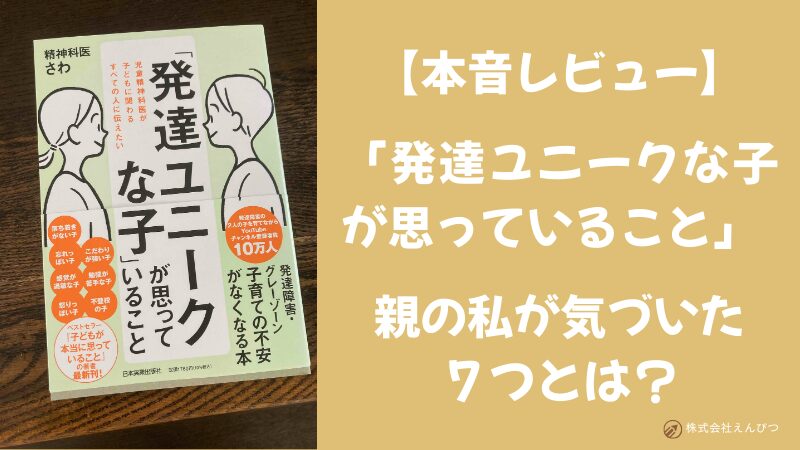
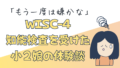
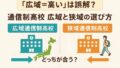
コメント